9 腹診による「毒」と「邪気」の診察と鍼灸治療
大浦慈観著 ヒューマンワールド 2016年
日本の漢方医学(漢方処方、鍼灸など)で重視され、独自の発展してきた腹診。中国では脈診が重視され腹診は衰退してきたという見方もあります。
日本の江戸期の鍼灸術を探るうえでも腹診は大変重要な部分ですが、残念ながら不明な部分も多いです。
本書では大浦慈観先生(師である横田観風先生)の独自の診断と治療法が解説されています。
8 刺鍼技術史
松本弘巳著 谷口書店 2002年
中国から日本に伝わり独自のものへと変化してきた鍼灸医学。その中の刺鍼技術(鍼の操作方法)について、中国での変化から日本に伝わり現代までの技術の変遷、流れをおおまかに概観することができます。
今年(2017年)当院の年賀状に使用したのは江戸時代に書かれた「鍼灸重宝記」にある打鍼の図です。鍼と槌を使う日本独特の技術です。この打鍼を使う流派で有名なのが無分流です。無分流について書かれた書物に「鍼道秘訣集」があります。
この「鍼道秘訣集」~心持の大事~に
「他流には何れの病には何れの処に何分鍼立てるなどと云う事計に心を盡(つ)くし、一大事の処に眼(まなこ)を付けず。当流の宗とする処は、鍼を立る内の心持を専とす。
語に、事わざに無心にて心に無事なれば、自然に虚にして霊空にして妙。挽ぬ弓、放ぬ矢にて射る日は中らず、しかもはづさざりけり。是、当流心持の大事なり。此の語歌を以て工夫し、鍼すべきなり。」
参考文献~弁釈鍼道秘訣集 藤本蓮風著 自然社 1978~
とあります。奥が深いですね。
7 石坂流鍼術の世界
町田栄治編著 三一書房 1985年
鍼灸の技術も他の日本文化と同じく江戸時代に、より洗練され、多く流派が生まれました。石坂流は杉山流の流れを汲み、11代将軍家斉の侍医を務めた石坂宗哲(1770~1841)が確立した流派といわれています。宗哲はシーボルトに鍼術を伝えた事でも有名です。
本書によると著者である町田栄治先生は宗哲とも交流のあった鍼医の家系に生まれたそうです。石坂流の修行について技術的なことは「…いいえ教わりません。みていて自分で工夫することです…」17~18ページとあます。
本書を読んだ私感として、技術の改良も含め石坂流というより町田栄治先生独自のいわば町田流といった印象を受けました…。
実は、まだ鍼灸学校の学生だった頃に町田先生が東京の神保町で詩画展を開催されていて、お会いすることが出来ました。その時に購入した「石坂流鍼術の技法」です。この時お伺いしたお話もメモして置いたのですが…出てきた時に追記したいと思います。
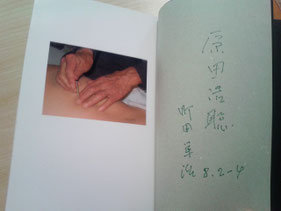
その時に書いて頂いたサインです。
6 神道のこころ
葉室賴昭著 春秋社 1997年
著者(昭和2年~平成21年)は公家の家系に生まれ、形成外科医院を開業、その後神職最高階位・明階を取得され牧岡神社と春日大社の宮司になられました。
本書の第二章に東洋医学のふしぎ(鍼治療と東洋医学、つぼの話…)があり、鍼灸治療の効果を高く評価され、臨床にも使われていたようです。
「神道というのはもともと信仰ではありません。本来、日本人の生活、知恵をさして神道と言っていました。」
日本人が忘れかけてしまった、生かされていること、感謝することの大切さについて語られています。
5 よくわかる黄帝内経の基本と仕組み
左合昌美著 秀和システム 2008年
「黄帝内経(こうていだいけい)」は中国古代の戦国時代(紀元前400~200年)頃に書かれた中国医学の根本とされる本です。現在に「黄帝内経」とされ伝えられているのは「素問(そもん)」と「霊枢(れいすう)」という本です。
黄帝内経を読む前に、こちらを読んでおくとより全体像と重要なポイントを理解しやすくなりますね。
4 野口晴哉・整体入門 正しい健康を生みだす秘訣
講談社 昭和52年
療術の世界で名人といわれる野口晴哉(のぐちはるちか 1911~1976)先生の講談社から出版された著書です。
今はよく知られるようになってきましたが、野口先生の整体は一般にイメージするものと違い繊細でより本質的なものです。
野口先生の一連の著作は、治療に携わる者には外せない、貴重な示唆を与えてくれます。
~異常を除いて正常であろうと考えている養生人は多いが、問題は異常ではない。問題は異常の中に正常を保っている体の働きである。それがどのように働いているのか、それを確かめることに養生の道がある~(月刊全生より)
3 はりきゅうロード 鍼灸OSAKA 別冊ムックVol.2
森ノ宮医療学園出版部 2012年
鍼灸や漢方(薬草)などに関する歴史や史跡、資料の在りかについて
豊富な写真とともに楽しく解説されています。
本書の中で、特に大浦慈観先生の「報恩の人 杉山和一」には
選鍼三要集→入江流門下生たちが論及
鍼灸大和文(砥寿軒圭菴)→療治之大概
杉山和一が参考にした流派として、入江流以外に無分流、妙鍼流
など短い文章の中に大変貴重(重要)な情報がサラリと纏められています。
2 尾台榕堂物語 ~越後妻有が生んだ漢方医学の最高峰~
漫画 斉藤ひさお 榕堂会 2010年
尾台榕堂(おだいようどう)は幕末期の名医で、浅田宗伯(あさだそうはく)と並び称されました。
吉益東洞(よしますとうどう)の古方漢方の系譜で、尾台浅嶽に師事。
貧しい人にも親切に治療にあたり、徳川家茂の侍医をも勤めたそうです。
この本は、題字 矢数道明・監修 藤平健・解説 小曽戸洋と
漢方、東洋医学界の錚々たる顔ぶれです…。
1 病の世相史 ~江戸の医療事情~
田中圭一著 ちくま新書 2003年
江戸時代の庶民の医療事情について、庶民と医療、医者とののかかわり、健康に対する考え方など、誤った先入観に気づかされる一冊です。
あとがき より
…わたしたちは、江戸時代に日本人が作り上げた独自の文明を、
もう一度見なおすべき時代をむかえているように思う…